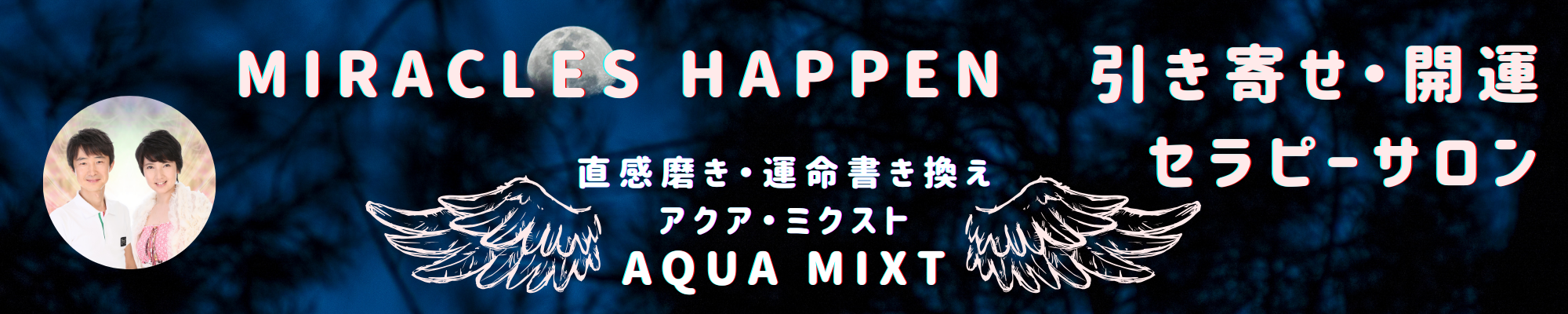マスターは東儀 宗介(とうぎ そうすけ)、かつて天使だった頃の名は、メネフィール (Menephiel)。
仕事帰りや週末に通う常連OKは、小鳥遊 紬(たかなし つむぎ)、28歳。中堅デザイン事務所のグラフィックデザイナー。
夜の帳が下りた路地裏、『刻詠珈琲店』の暖かな灯りが、今日も紬を迎え入れる。カウンターの向こうで、宗介が静かにコーヒー豆を挽く音が響いている。
「マスター、また来ちゃいました……もう毎日のように質問ばかりで、うんざりしてませんか?」
「どうぞ。」
宗介は何も言わず、柔らかな微笑みを紬に向けて、淹れたてのコーヒーをそっと差し出した。
「ありがとうございます……。あの、よく『カードに呼ばれた』とか『ピンときた』とか聞くんですけど、私、そういう感覚が全然分からなくて。カードが『私を選んで!』って言ってるなんて、どうやったら感じられるんですか?」
紬は困惑した表情でカップを両手で包んだ。
「いただきます。」
「呼ばれる、ですか。確かに言葉にするのは難しいですね。」
宗介はゆっくりとカウンターを拭きながら続けた。
「でも、それは特別な能力じゃないと思いますよ。紬さんにも必ずある感覚です。」
「私にもですか? スピリチュアルな才能なんて、全然ないと思うんですけど……。」
「才能の話ではないですよ。たとえば、君がこの店を見つけた時のことを思い出してみてください。」
「えっ?」
「大通りから、なぜこの路地に入ったんでしょうか?」
紬は記憶を辿るように目を細めた。
「そういえば……特に理由はなかったんです。
ただ、なんとなく気になって、ふらっと入ってみたら、この店があって……。」
「その『なんとなく』が、呼ばれるということだよ」
宗介の言葉に、紬の目が大きく開かれた。
「えっ、それだけ?」
「ええ、それだけです。紬さんの心が『ここに何かある』と感じ取ったんです。理屈でもなく、説明も難しいかもしれませんね。でも確かに感じた何か。それが直感というものです。」
宗介は古い万年筆を手に取り、くるくると回しながら話を続けた。
「僕たちは普段、頭で考えることに慣れすぎているようです。評判はどうか、値段は適正か、レビューは良いか。そういった情報で判断することが当たり前になっています。」
「まさに私です……。カード選びでも、ずっとレビューばかり読んでました。」
「もちろん、それも大切なことですよ。でも時には、その思考の声を少し静めて、心の奥から湧き上がる小さな声に耳を傾けてみるといいと思います。」
宗介はハンドドリップしたてのコーヒーポットから紬のカップに注ぎ足した。
「その声は、ひょっとしたら、風が窓を撫でるような、本当に小さな音かもしれません。『気になる』『なんか好き』『ちょっと惹かれる』。そんな些細な感覚ですね。でも、それこそが紬さんの直感が発しているサインです。」
「でも、もしそれが勘違いだったら?間違ったカードを選んじゃったらどうしよう、って」
「勘違いでもいいじゃないですか。」
宗介の声は穏やかだった。
紬の不安な気持ちをそのまま包み込むように言葉を続けた。
「直感は筋肉と同じだと思います。使わなければ衰えるし、使えば使うほど鍛えられます。最初から完璧な直感を持つ人なんていないですよ。紬さんが『なんとなく』を信じて行動するたびに、その感覚は少しずつ研ぎ澄まされていきます。大丈夫ですよ。」
紬は自分の手を見つめた。
「私にも、ちゃんとあるんですね。直感って」
「もちろんですよ。紬さんがこの店に辿り着いたように、必要なカードも紬さんを呼んでくれます。ただ、その声はとてもほのかなものだから、心を静めて耳を澄ます必要はありますね。」
宗介は棚からオラクルカードのデッキを取り出し、扇状に広げてみせた。
「試してみますか?何も考えず、ただ心が動くカードを一枚選んでください。」
紬は深呼吸をして、カードをじっと見つめた。
数秒後、彼女の手が自然と一枚のカードに伸びた。
「あ……、このカード、なんだか温かい感じがする!」
「それが『呼ばれる』ということですよ。」
宗介の口元に、かすかな笑みが浮かんだ。
「次にカードを選ぶ時は、その感覚を信じてみるといいですよ。頭で考える前に、心が動く方向に従ってみようって。きっと素敵な出会いが待っているはずです。」
「はい!今度は思い切って、直感を信じてみます!」
窓の外では、静かに雨が降り始めていた。
その音もまた、心の声に耳を傾けるための、優しい伴奏のようだった。