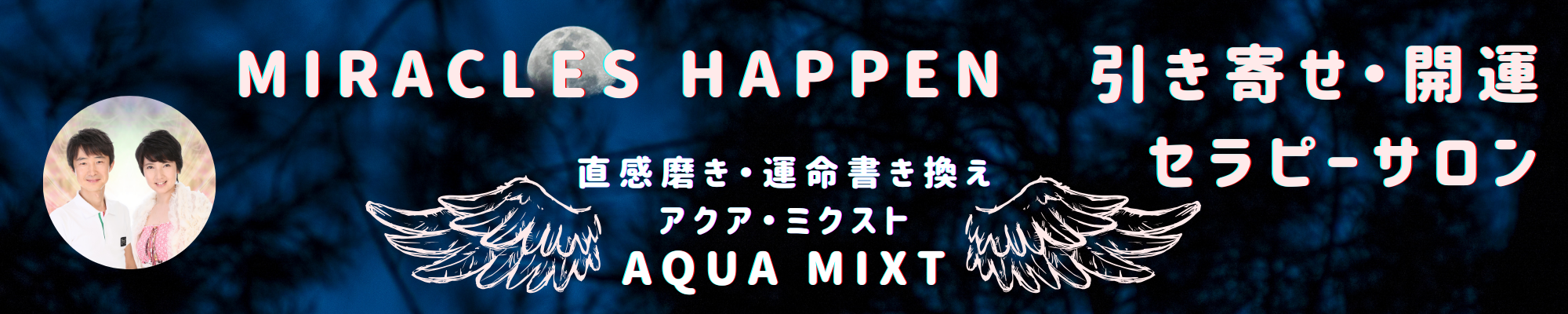人は人生に「物語」を求める。
それは生きているという実感を持つためかもしれない。
その感情を激しく揺さぶるような「物語」があることで人は奮い立ち、怖れを克服することもある。
その反面、その「物語」は人生の大きな障害となって立ちはだかり、
人を鍵のかかっていない牢獄に拘禁することもある。
「物語」は二極性を取り込み、さらに躍動感のあるものとなる。
二極性とは、ポラリティなどと訳される。
「挫折・成功」「希望・絶望」「歓喜・悲痛」「優勢・劣等」「生・死」
「躁状態・鬱状態」「賛成・反対」「順風・逆境」「幸福・不幸」…。
その単語を目にしただけで、心が沸き立つこともあるかもしれない。
または、身体がこわばるような氣持ちになるかもしれない。
「物語」は「トラウマ」「ドラマ」と呼ばれることもある。
または、「脚本」「大義名分」「信念」「観念」などとも名を変えることもある。
なぜか、彼は学生時代から、多くの人の相談を聴く機会に恵まれた。
「恵まれた」と言えるようになったのは、ここ数年だが、
当時は「またか…!?」と厄介な仕事を引き受けるような氣持ちだった。
しかし、彼はそれをすべて受け入れていたし、
その犠牲的な身のささげ方に酔いしれているところもあった。
自分の時間を他人に捧げている感じ。
自分のやりたいことを我慢している時。
他人の痛みや苦しみのほうが強く感じられ、自分をなおざりにしておく感じ。
ある時、その彼女の相談を受けることになった。
彼女は、恵まれない家庭に育ったようだ。
これまで彼女が体験してきた苦しみや悲しみを涙ながらに話してくれた。
彼はその話を聴きながら、自分の境遇と重ね合わせていた。
自傷行為を繰り返す彼女のために何か話を聴く以上のことができないか?と彼は思い始めるのだった。
「わたしなんて、誰にも愛されていませんから。」
「わたしは本当に愛されて生まれてきたのかなぁって思ってしまうの。」
「お父さんに言われた『本当は長男が欲しかった…。』という言葉、今でも思い出して泣いてしまう。」
「自分のことを粗末にしている感覚が好き、どんよりとして恍惚感にあふれていて。」
「神さまに裏切られたと思っているの、そんなわたしを使ってこの世の中に復讐したいと思っている。」
彼女が話の合間に呟くようにいう言葉が彼の胸に突き刺さるのだった。
「きみは愛されて生まれてきたんだよ。」
「愛されているから、こうして今、生きているんだよ。」
こうした言葉を彼女に投げかけながら、
自分すら「愛されていること」に自信がないのだから、自分のその言葉の嘘臭さを感じていた。
「愛された、愛されている」という実感はこうまでも人生に大きな影響を及ぼすのか…。
その嘘臭さを払拭するために、
彼女の人生に何かしら大きなものを与えるために、
彼は決断したのだった。
彼女を救えるのは、オレしかいない。
「オレがそばにいるから。」
「オレと一緒に乗り越えていこうよ。」
「心中したって、いいよ。」
「一緒に不幸になる覚悟はあるよ。」
と伏し目がちな彼女に向かって投げかけた。
「貢献」という氣持ちを感じ、彼はエクスタシーに達していた。
彼女を道具のように扱い、自分だけのために使っていたことに氣づくのはしばらく経ってからだった。
彼の「愛への彷徨」はその後も続く。
ポラリティ中毒は物事をそのままに観ることから遠ざける。
その恍惚感の代償は大きい。