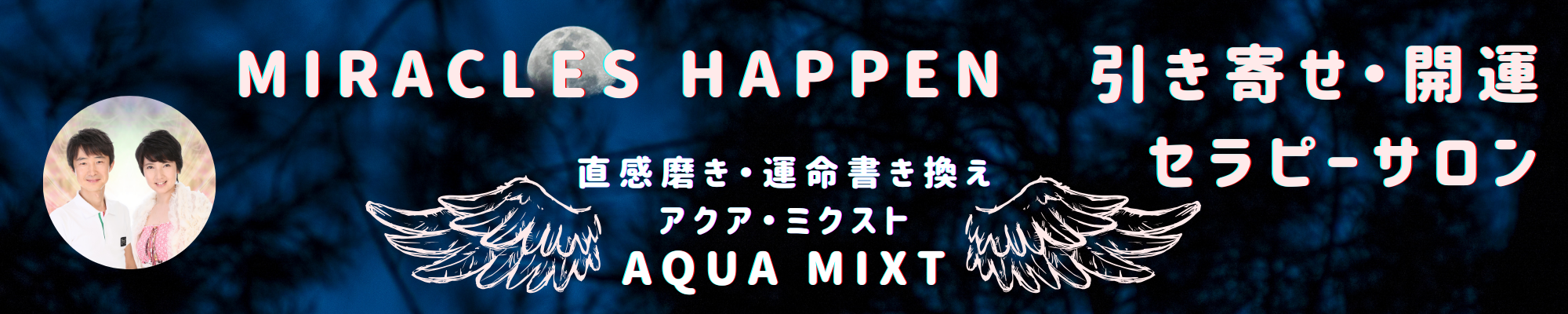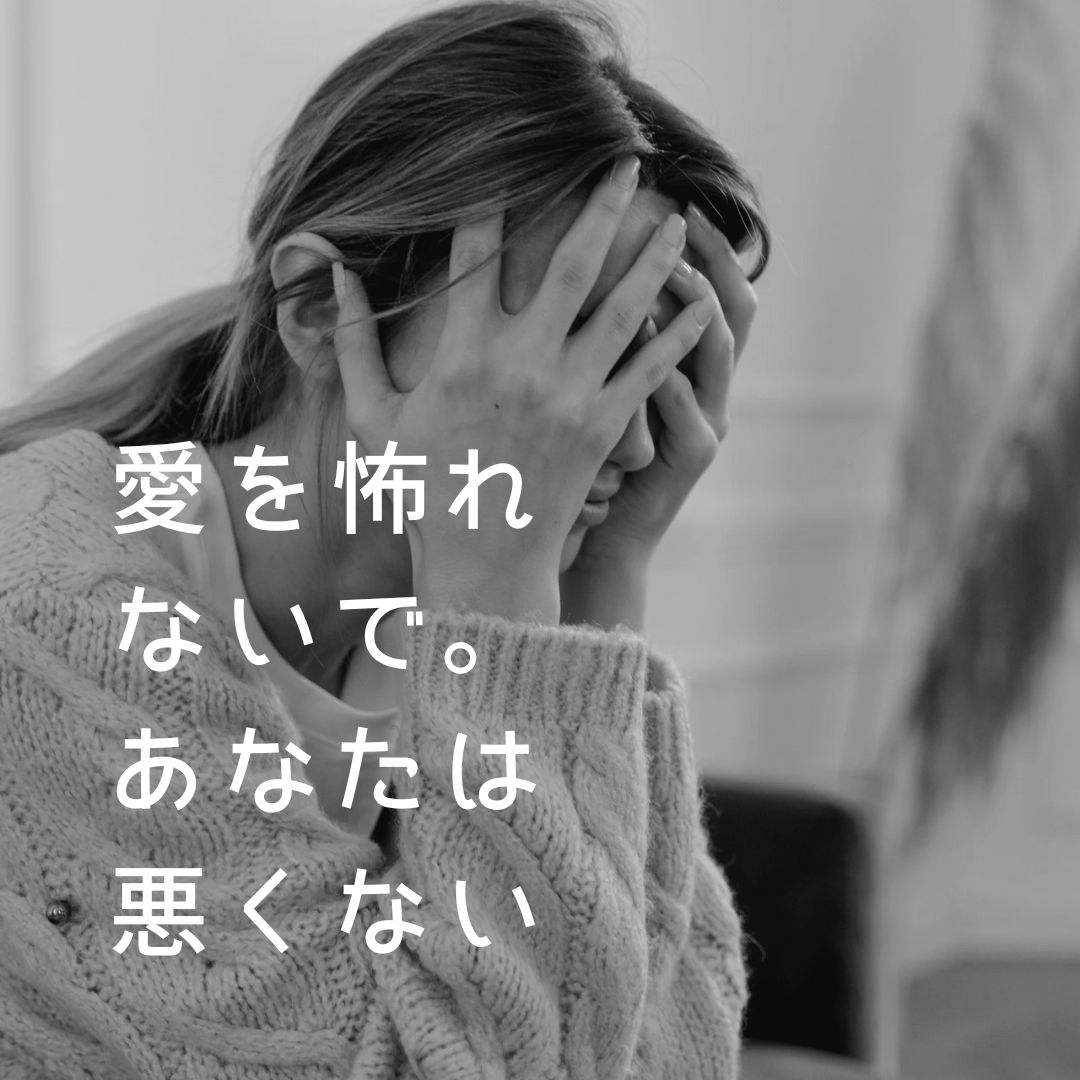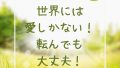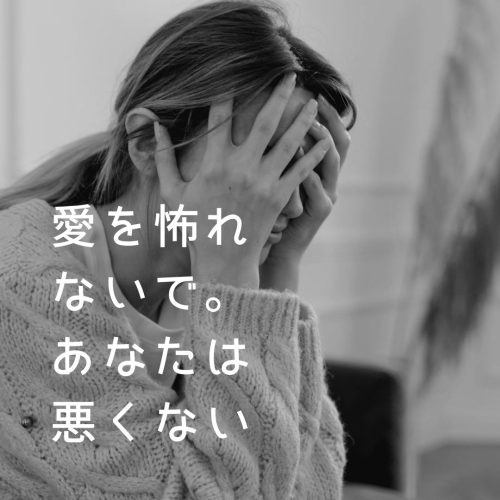
怖くて前に進めない
「どうせやっても無駄だ…」
「頑張ったってどうせ変わらない…」
多くの失敗や叱咤、ダメ出しにより、その心は傷つき、『どうせ無理』という思い込みでいっぱいになってしまうことがあります。もしかしたら、あなたも今、そんな気持ちを抱えているのかもしれませんね。
あなたが抱えているその痛み、僕はとてもよく理解できます。なぜなら、僕自身もまた、何度も立ち上がり、乗り越えてきたからです。
新しいことに挑戦する時、
人間関係で悩んだ時、
人生の壁にぶつかった時、
僕たちは時に、無力感に襲われ、身動きが取れなくなってしまうことがあります。 スピリチュアル・心理カウンセラーとして、日々多くの方の心の声に耳を傾けているので、誰もが日常的に体験することと感じています。
特に最近のカウンセリングセッションでは、
「やってみたいことがあるが、怖くてできない」というテーマを抱える方が多く、その背景には、他人の評価を気にしすぎる、失敗を恐れる、自分で決断することへの不安といった心理的な要因が深く関わっていると感じています。
また、当たり前のように評価教育を受け容れ、自己信頼が低いことも要因でしょう。
そして、これらの問題の根底には、「学習性無力感」という心理学的な概念が深く関わっていることが多いのです。
学習性無力感とは?
学習性無力感とは、自分の行動が結果に結びつかない経験を繰り返すことで、
「何をしても無駄だ」と感じてしまう状態を指します。
心理学者のセリグマンは、犬を使った実験が有名です。
犬を2つのグループに分け、一方のグループの犬には、電気ショックを止めることができるレバーを与え、もう一方のグループの犬には、電気ショックを止めることができないようにしました。
その後、どちらのグループの犬にも、逃げることができる状況を与えたところ、電気ショックを止めることができた犬は、すぐに逃げ出しましたが、電気ショックを止めることができなかった犬は、逃げることを諦め、電気ショックを受け続けたのです。
怖ろしすぎる実験ですね…。
この実験から、セリグマンは、
「自分の行動が結果に影響を与えない」という経験を繰り返すことで、無力感を学習してしまうことを発見しました。
たしかに、セリグマンの実験は、僕たちに深い衝撃を与えます。
しかし、同時に、そこから学び、克服する方法もあることを知っておいてほしいと思います。
学習性無力感のメカニズム
学習性無力感は、私たちの認知、感情、行動に影響を与えます。
認知的には、
- 「どうせ無理だ」「頑張っても無駄だ」といった否定的な思考パターンが形成される
- 成功体験を過小評価し、失敗体験を過大評価する
- 将来への希望を持てなくなる
感情的には、
- 無気力、絶望感、抑うつ感、不安感、罪悪感などを感じやすくなる。
- 感情のコントロールが難しくなる
行動的には
- 新しいことに挑戦することを避ける
- 問題解決のための行動を起こさなくなる
- 受け身的な態度になる
といった傾向があります。
学習性無力感の要因
学習性無力感は、様々な要因によって引き起こされます。
- 過去の失敗体験
幼少期の虐待やネグレクト、学校でのいじめ、仕事での失敗など - ダメだし(否定的フィードバック)
常に否定的な言葉を浴びせられる、努力を認められないなど - コントロールできない状況(主導権を握られる)
自分の意見が反映されない、決定権がないなど - 完璧主義
完璧を求めすぎるあまり、失敗を恐れて行動できなくなる - 社会的要因
競争社会、格差社会、不況など
日本の義務教育の問題点
日本の義務教育においては、一方的な評価を重視し、自主性や自己肯定感を育てる教育が不足しているという問題があります。
特に、悲しみや怒りといった感情を適切に表現することを抑圧されることで、子どもたちは、感情を抑圧し、コントロールすることを学び、学習性無力感に陥りやすい傾向があります。
- 泣くことを我慢させられる
- 怒ることを禁止される
- 自由な発言を制限される
- 自分の意見を言うことを否定(評価)される
このような経験を繰り返すことで、子どもたちは、自分の感情を抑圧し、自分の行動が結果に結びつかないことを学習し、無力感を感じてしまうのです。
学習性無力感から抜け出すための道標
では、学習性無力感に陥った場合、そこから抜け出し、自分の人生を力強く生きていくためには、どうすれば良いのでしょうか?
自分の感情に気づき、表現する
自分が何を感じているのか、その感情に気づき、それを言葉や行動で臆することなく、怖れずに表現することが大切です。
そして、悲しみや怒りを感じた時は、無理に抑え込まず、泣いたり、分かち合って話したり、書いたりするなど、自分に合った方法で表現してみることです。また、芸術的な表現(文学、マンガ、映画、演劇など)を通して、自身の感情を理解し、昇華させるという方法もあります。
認知の歪み(思い込み)を修正する
「どうせ無理だ」「頑張っても無駄だ」といった否定的な思考パターンに気づき、それを現実的な思考に置き換えてみます。そのために、今までの成功体験を振り返り、自分の能力を肯定的に評価してみることです。
否定的な感情をいつまでも覚えている傾向が人にはありますから、積極的にこの振り返りはする必要があります。
小さな成功体験を積み重ねる
日常的に、小さく達成可能な目標を設定し、それを達成することで、自己効力感を高めるという方法もあります。ひとつの目標もその達成までのプロセスを細かく分け、一つずつクリアしていき、成功体験を記録し、自分の成長を実感してみるといいでしょう。
「こんなことができたところで…」と自己否定するのはしばらくやめてみましょう。
コントロールできることに焦点を当てる
自分がコントロールできることと、コントロールできないことを区別してみます。コントロールできないことに意識を向け続けるのは、疲れますから…。
ですので、コントロールできることに焦点を当て、積極的に行動してみましょう。コントロールできないことについては、受け入れるか、状況を変えるための行動を起こすといったように工夫してみましょう。
「雨が降ったら傘をさす」は我が家の教育方針です。
サポートシステムを構築する
信頼できる人に相談する
カウンセリングを受ける
同じような経験をした人と交流する
学習性無力感と上手に付き合っている人と仲良くなりましょう。できれば、日常的に相談してみるといいでしょう。
これらの道標を参考に、学習性無力感に陥った場合、そこから抜け出し、自分の人生を力強く生きていくことができます。
そして、僕たち自身が、自分の感情と丁寧に向き合い、自分の人生を切り開いていく姿は、周りの人々にも勇気を与え、希望の光となるはずです。