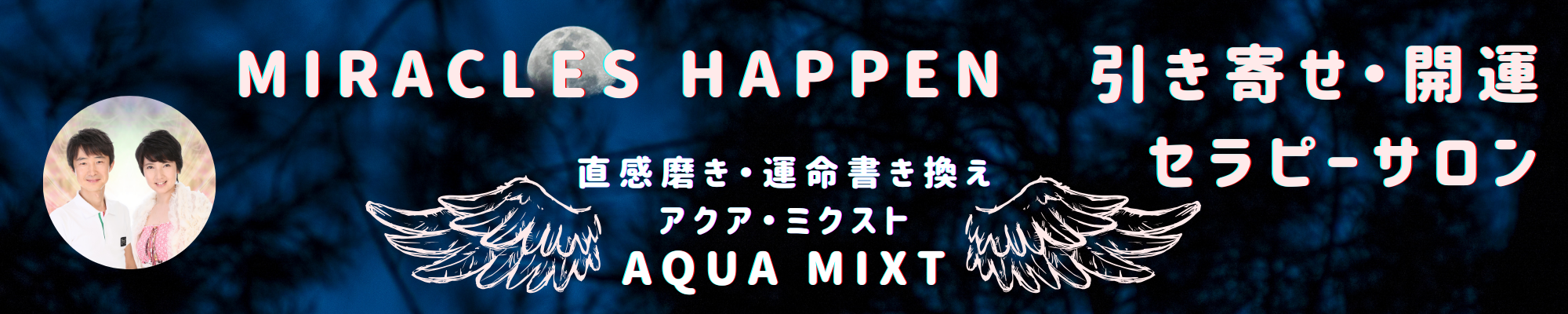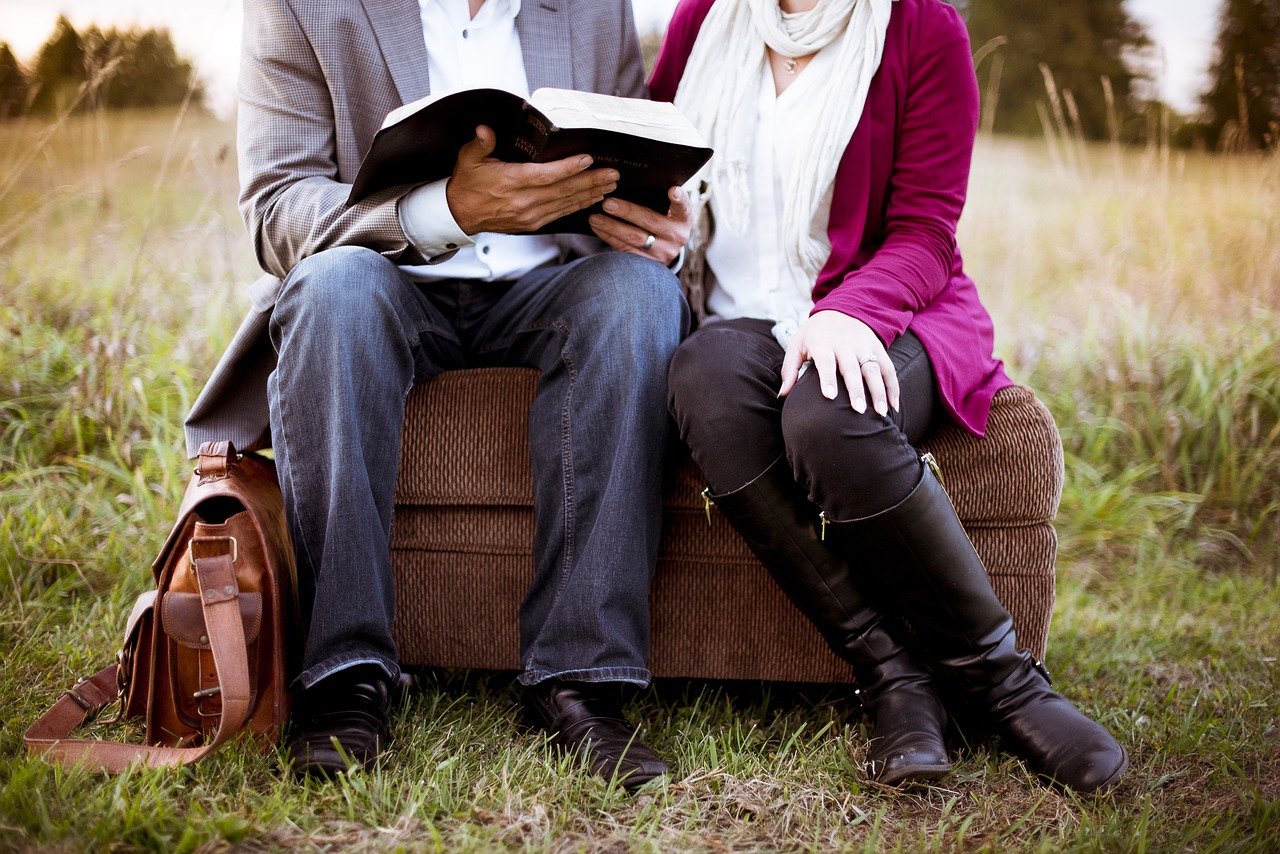男性と女性は違う生きものである
これは学生時代の僕にとって大きな研究テーマでした。
「人間ってどんな生きもの?」
「男性と女性は違う生きもの?」
「どうして喧嘩をするの?」
という子どもの頃から、機能不全の家庭に生まれ、感じていた疑問でした。
それを解消するために、心理学を学びました。
少しでも男性と女性の違いを理解し、自分の不安を解消したかったのです。
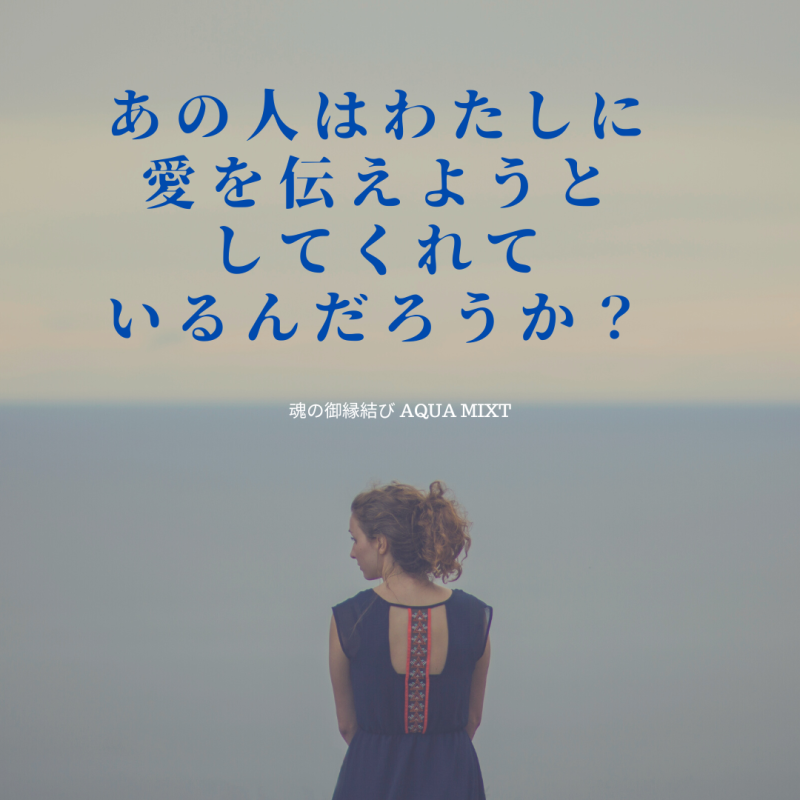
そして、それは男性→女性、女性→男性の愛し方の違いにもつながります。
愛し方の違いに不安になる人も多い
AQUA MIXTは夫婦ふたりで運営してきましたが、この性差による衝突や不安は数多く、「どうして?」「なんで?」という思いを持つことも多々ありました。
愛し方に違いがあるために、相手の好意を受け取れないことも、自分の好意が伝わらないことも日常茶飯事です。それを理解するのには時間と話合いが必要でした。
お互いの言動にどんな意味があるのか?
それはお互いに正直になる必要がありました。
僕が家事をするのは、家族への愛情表見のひとつですが、妻からは「家事の好きな人」をいう認知でしかありませんでした。
その違いは、何を生みだすかは想像に難くないと思います。
一言、相手に「愛しているよ」と伝えればいいのに、分かりにくい愛情表現をしてしまうところに男女の存在価値があると言えるでしょうか。

男性が貴女を心配したくなるのは、どうしてなのか?
いきなり、男性が貴女に怒ってきたことはありませんか?
「ちゃんと○○してくれないと困るじゃないか!」
「母親なんだから、ちゃんとしてくれ!子どもたちが可哀想だ!」
「メールしたら、すぐに返信してくれ!大人として常識だろ?!」
「ひとりでそれをするのは危ないよ!いい加減にしろ!」
などなど。
これらの言葉と感情は、「あなたを愛しています」という表現のひとつです。
しかし、男性は自分の氣持ちを自分で味わい、本当の氣持ちを表現するのが苦手です。
特にその教育も受けていなければ、練習もしません。
それでも、何とか感情を表そうとするので、貴女にとっては逆効果であることが多いです。
うるさいな!放っておいてよ!
という男性にとっては一番言われたくない言動を自ら誘ってしまっています。
残念な結果になるでしょう。
相手の愛し方と自分の愛し方の溝を埋めよう
貴女にとっては意味不明なものとなるひとつ…
男性の勝手読みを理解する必要があります。
【勝手読み(かってよみ)】
相手の応手をしっかり考えずに、自分に都合のいい手順を読むこと(囲碁用語)。
男性の多くは、理解し合おうとするコミュニケーション技術を磨かずに大人になります。
日本の「男尊女卑」がその風潮を後押ししているかもしれません。
男性が何を伝えているつもりなのか?
まるでクイズのような瞬間を女性なら体験したことがあるでしょう。
以下、イメージしながら読み進めてみてください。
- 今の仕事で業績をあげたことをあなたに得意げに話す
- 健康診断で引っかかってしまったことをことさら大げさにあなたに話す
- 昔はモテたという自慢話をあなたに楽しそうに話す
- 後輩の面倒を仕方なく自分が見ていると愚痴る
- 急に不機嫌になって黙る
- あなたへの誕生日プレゼントが彼の好きなもの
- あなたとのデートは彼が行きたい場所優先
- あなたへの連絡の頻度は彼次第
など、どうでしょうか?
彼はあなたに何を伝えているつもりなのでしょうか??
男性が隠している本音が手に取るようにわかったら、あなたのとるべきコミュニケーションは楽に決まっていきます。愛ももっと感じ取れるようになります。