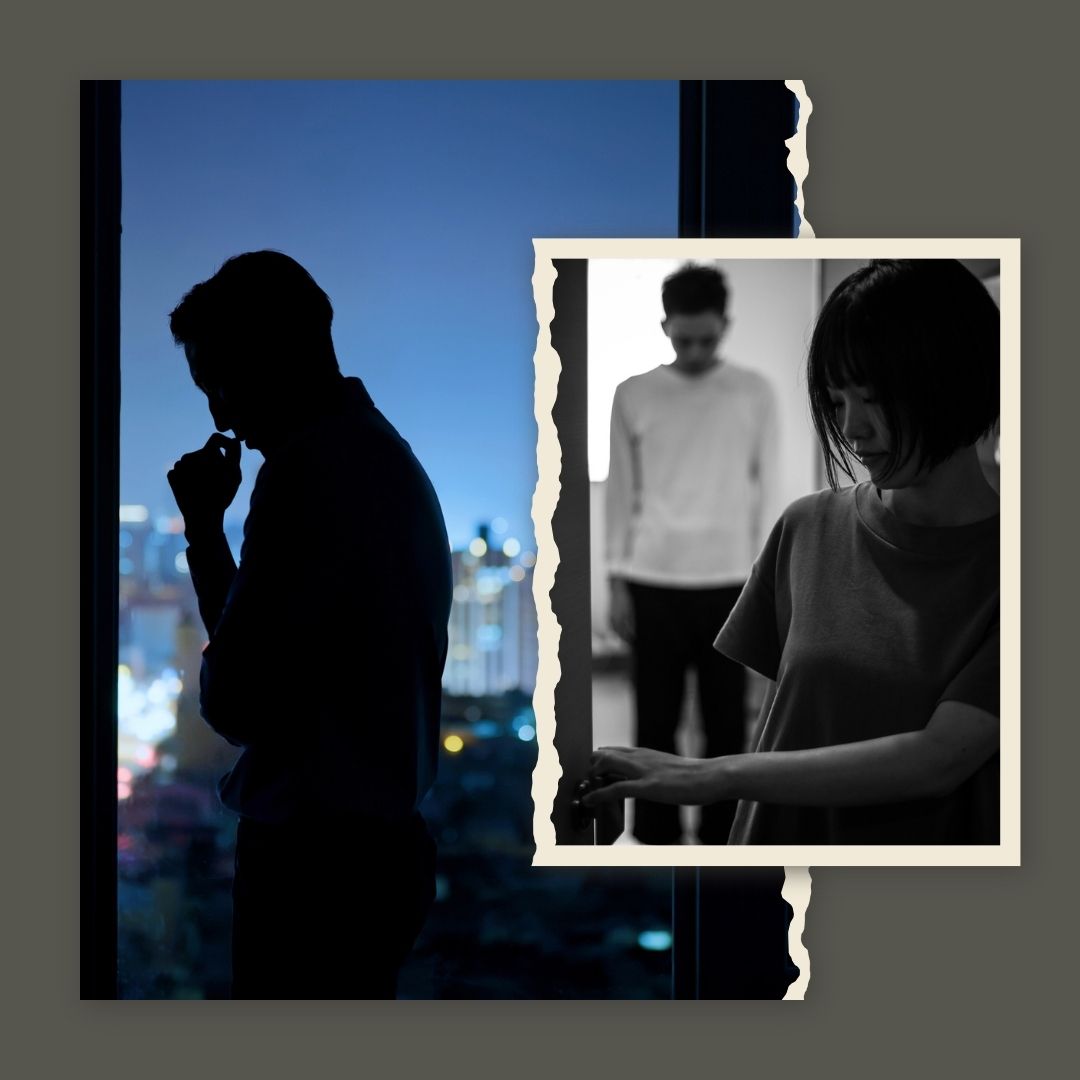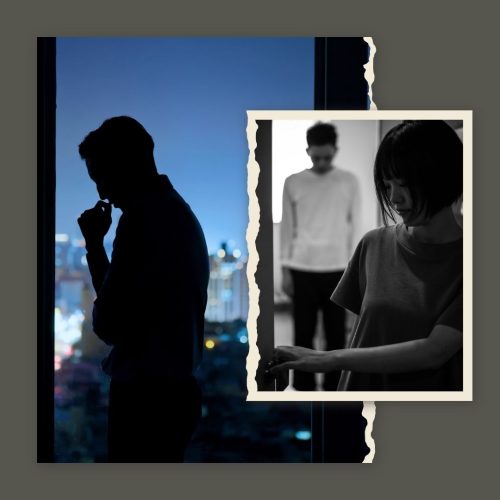
「がっかり」の言葉に傷つかないために
「あなたにはがっかりさせられた」
「残念だよ」
「期待外れだった」
これらの言葉を、大切な人から言われた経験はありませんか?
親しいパートナー、友人、家族、あるいは尊敬する人から。
その言葉は、まるで心の深いところに突き刺さる棘のように、わたしたちを深く傷つけ、立ち直るまでに長い時間を要することもあるかもしれません。
もしかしたら、あなた自身も、大切な人に、同じような言葉をかけてしまった経験があるかもしれませんね。

省みるとわたしもそうです。
この文章では、わたしたちが「他人からの評価」にどのように向き合えば、心の平穏を保ち、より健全な人間関係を築けるのか、心理学的な視点も交えながら、一緒に考えていきたいと思います。
「あなたにはがっかりさせられた」という言葉の衝撃
「あなたにはがっかりさせられた」という言葉は、なぜ、これほどまでにわたしたちの心を揺さぶるのでしょうか。
心理学者のカール・ロジャーズは、自己概念(自分がどのような人間であるかという認識)の形成において、「他者からの評価」が大きな影響を与えることを指摘しました。
わたしたちは、幼い頃から、親や教師、友人など、周囲の人々からの評価を通して、自分自身を認識していきます。
例えば、
子どもの頃、テストで良い点を取れば褒められ、悪い点を取れば叱られるという経験を繰り返すことで、「良い点を取る自分は価値がある」「悪い点を取る自分は価値がない」というように、自己評価が他者の評価に左右されるようになってしまうことがあります。とくに日本の学校教育は唯一解を求める傾向にありますから、間違えることに臆病になります。
大人になった今でも、このパターンが潜在的に残っているため、「あなたにはがっかりさせられた」という言葉は、わたしたちの根深い部分に触れ、大きなショックを与えるのです。
自分自身が商品であるという感覚
現代社会において、わたしたちは、多かれ少なかれ、自分自身を「商品」として市場に出し、評価される立場にあります。個人事業主であればなおさらでしょう。
例えば、
SNSでの発信、仕事での成果、趣味の活動など、あらゆる場面で他者からの評価がつきまとうと言えるでしょう。
わたし自身、AQUAMIXTにおいてスピリチュアル・心理カウンセラーとして活動する中で、クライアントさんからの評価は、活動を続けていく上で、とても大切な指標となります。
しかし、それが、親しい人、パートナー、友人、家族など、大切な人からの評価となると、話は少し複雑になります。
なぜなら、わたしたちは、大切な人との関係性において、損得勘定や効率性だけでなく、愛情、信頼、共感といった、より深い心の繋がりを求めているからです。
そのため、大切な人からのマイナスの評価は、わたしたちの心の深い部分に触れ、大きなショックを与えることがあるのです。
昨今、よく耳にする「エゴサーチ」という行為も、「他人からの評価」が気になるがゆえの行動と言えるでしょう。
「評価」という名のコントロール
人間関係において、「評価」は、時に、相手をコントロールするための道具として使われることがあります。
心理学者のエリック・バーンは、著書『交流分析入門』の中で、人間関係における様々な「心理ゲーム」について解説しています。
ここでいう「心理ゲーム」とは、無意識的に繰り返される、不健全なやりとりのパターンのことです。
例えば、
「あなたにはがっかりさせられた」という言葉は、相手に罪悪感や劣等感を抱かせ、自分の思い通りに動かそうとする「心理ゲーム」の始まりとなることがあります。
このような「心理ゲーム」を仕掛ける人は、相手がどのような言葉に傷つきやすいのか、どのような言葉に反応するのかを、経験的に知っています。
そして、自分の都合の良いように相手をコントロールするために、意図的、あるいは無意識的に、それらの言葉を使い分けているのです。

あなたも、過去に、そのような人のコントロール下に置かれた経験があるかもしれません。
彼らが意図的に行っているのか、幼い頃からの経験を通して身についたものなのか、それは神のみぞ知るところですが、わたしたち誰もが、多かれ少なかれ、このようなコントロール思考を持っていると言えるでしょう。
大切なのは、そのような思考に気づき、それを選択しないという「心の自由」を持つことです。
心に突き刺さる「評価の言葉」を客観的に見つめる
人と良い関係を築こうと、相手に近づいたにもかかわらず、
「あなたにはがっかりさせられた」
「そういうこと言うの、残念だよ」
「期待して損した。裏切られた気分」
などと言われたら、心が深く傷つき、立ち直るまでに時間がかかるかもしれません。
このような時、心理学者のアルフレッド・アドラーは、著書『嫌われる勇気』の中で、「課題の分離」という考え方を提唱しています。
「課題の分離」とは、自分の課題と他者の課題を明確に区別し、他者の課題に介入しないという考え方です。
例えば、
「あなたにはがっかりさせられた」という言葉は、相手の課題であり、あなたがコントロールできるものではありません。
相手は、あなたに期待しているのかもしれません。
相手は、あなたに要求しているのかもしれません。
相手は、あなたに依存しているのかもしれません。
相手は、あなたと共に同じ感情を共有したいと思っているのかもしれません。
特に、あなたが、
「人の期待に応えたい」
「周りの人に良い影響を与えたい」
「人と調和したい」
といったことを強く願っている場合、相手の強い言葉は、あなたの心に深く突き刺さり、大きなダメージを与えるでしょう。
しかし、ここで大切なのは、「〜された」という受動的な視点ではなく、「(相手は)〜している、と思っている」という能動的な視点を持つことです。
思考する時に「受動的」ではなく、「能動的」に文章を組み立てることで、あなたは、相手の言葉に振り回されるのではなく、自分の心の状態を客観的に見つめることができるようになります。
あなたは、受けたダメージを取り返そうと、相手の誤解を解こうとするかもしれませんが、そうすることで、いっそう相手の「こじれた交流(やりとり)」の中にハマっていくでしょう。
心理学者の交流分析では、このような「こじれた交流(やりとり)」を「心理ゲーム」と呼び、理解、回避、予防することの重要性を説いています。
あなたの心は自由 何を感じてもいい!
「あなたにはがっかりさせられた」という言葉は、わたしたちの心を深く傷つける力を持っています。
しかし、心理学的な視点から見ると、この言葉は、わたしたち自身の心の状態や人間関係のパターンを映し出す鏡のような存在でもあります。
大切なのは、相手の言葉に振り回されるのではなく、自分の心の状態を客観的に見つめ、思考のパターンを変えていくことです。
心の鎧を脱ぎ、他者からの評価との適切な距離感を保つことで、わたしたちは、より健全な人間関係を築き、心の平穏を保つことができるでしょう。
そして、何よりも、自分自身を大切にすることを忘れないでいましょう。あなたは、あなたらしく生きるだけで、十分に価値のある存在なのですから。