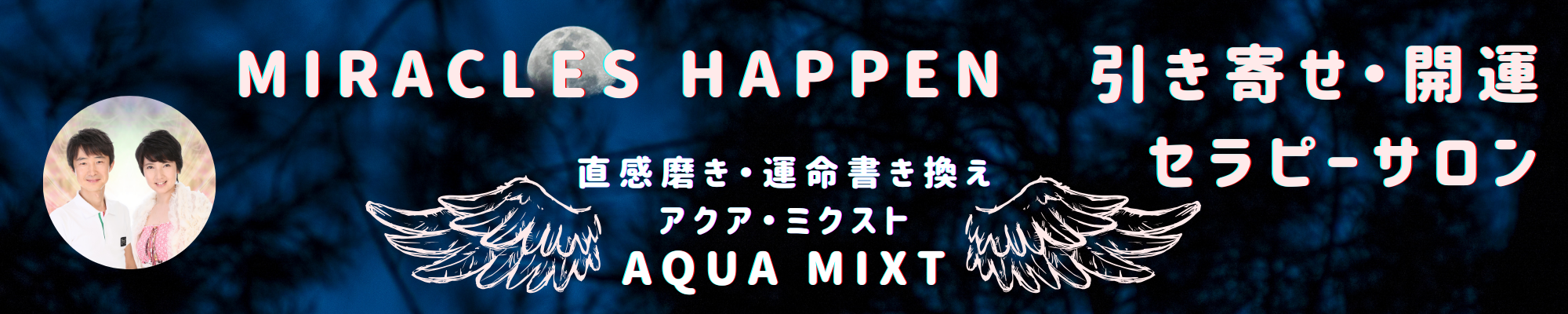「なんだか、恥ずかしい…」
あなたは、そんな風に感じて、思わず行動を止めてしまった経験はありませんか?
僕たちは、成長するにつれて、「恥ずかしい」という感覚を強く意識するようになります。「もう、いい大人なんだから、こんなことしてはだめだ…」と、自分を制止したり、過去の行動を恥じたりすることもしばしばあるのではないでしょうか。
そして、この「恥ずかしい」という感情は、時に、僕たち自身の心の中で、まるで強力な鍵のように、人生の可能性をロックしてしまうことがあります。
あなたの「恥ずかしい」という感覚は、誰のもの?
「他人に笑われるようなことをしてはいけない。」
「恥をかくようなことをしでかしてはいけない。」
こうした言葉は、多くの人が幼い頃から、親や教師、社会全体から繰り返し聞かされてきたのではないでしょうか。これらのメッセージは、やがて強い「思い込み」「信念」「決めつけ」となり、僕たちの心に深く根を下ろしていきます。
心理学では、このような思い込みが、私たちの自己概念や行動パターンを形成していくと考えます。特に、自分が傷つくことを避けるための「防衛機制」として、この「恥ずかしい」という感情が強化されていくことがあります。
周りにいる「失敗者」を見て、「自分はあんな風にならないぞ」と、心の中で優越感を感じたり、自分を正当化しようとしたりすることもあるかもしれません。しかし、皮肉なことに、このような「他人を反面教師にする」という行動もまた、自分自身が「失敗を恐れる」という思い込みを、無意識のうちに強化していることにつながるのです。
僕たちが人生に対して受け身になり、新しい挑戦を避けようとすればするほど、この「恥ずかしい」という思い込みは、その力を増していくようです。まるで、心の成長を阻む壁が、どんどん厚くなっていくと言ってもいいでしょう。
「恥ずかしい」と「面倒くさい」の本音
自分らしく生きようと決意し、自分の才能を信じて一歩を踏み出そうとする時、間違いなく、この「恥ずかしい」という感覚は、目の前に立ちはだかります。
そして、その「恥ずかしさ」を直接感じたくないがために、僕たちは、「ああ、なんか面倒くさいな…」と、別の感情にすり替えて、行動を避けることがあります。
しかし、この「面倒くさい」という言葉の裏には、
実は「恥ずかしい」という感情だけでなく、
「失敗への怖れ」
「自分の限界を知りたくない」
「他人からどう思われるかという不安」
といった、より深い怖れが隠れています。
「面倒くさい」と感じた時、それはあなたの心が、未知への一歩を踏み出すことに対する抵抗、あるいは過去の傷つき体験が呼び起こす警戒信号なのかもしれません。この「面倒くさい」の奥にある本音に気づくことが、行動を変える第一歩となるでしょう。
実体のない怖れを打ち砕く!心理療法「羞恥心粉砕法」
では、この私たちの人生をロックしてしまう「恥ずかしい」という感覚と、どのように付き合っていけば良いのでしょうか?
心理療法の中には、その名もずばり「羞恥心克服法」、あるいは「羞恥心粉砕法」と呼ばれるアプローチがあります。その名を聞くと、いささか物々しい印象を受けるかもしれませんが、これは、心理学的な根拠に基づいた、非常に有効な方法です。
この療法の基本的な考え方は、僕たちが「恥ずかしい」と感じる対象に対し、あえて意識的に、そして意図的に「恥ずかしい」と感じるような行動をとってみるというものです。
例えば、
異性とのコミュニケーションに強い苦手意識を持つ「異性恐怖症」の方が、人通りの多い公園などで、あえて見知らぬ異性に声をかけてみる。その声かけが、たとえどんなにたどたどしいものでも、笑われるような内容だったとしても、とにかく「やってみる」ことを繰り返すのです。
この「恥ずかしい」と感じる状況に、自ら身を置くことを繰り返すことで、次第に、羞恥心に対する認識が劇的に変わっていくことが分かっています。これまで、まるで実体のある「おばけ」や「幻」のように、僕たちを怯えさせていた「恥ずかしい」という感情が、実は、自分自身が勝手に創り出していた、単なる「ひとり芝居」だったのだと気づくのです。
羞恥心粉砕法は、まさに「認知行動療法」の応用とも言えるでしょう。
恐怖の対象に段階的に触れる「エクスポージャー(怖がっているものに、安全な形で慣れていくこと)」に近い効果をもたらし、今まで避けてきた状況に対する不安や、それによって生まれる非合理的な思考を修正していくのです。非合理な幻影を粉砕します。
「卑小な自分」を全肯定する
人は誰もが「無限の可能性を持つ存在」だと言われます。
しかし同時に、儚く、卑小で、か弱い人間でもあります。その等身大の自分、完璧ではない自分を、ありのままに認めたところで、僕たちの無限の存在としての可能性に全く影響はない、ということを知ることが大切かもしれません。
むしろ、儚く卑小でか弱き存在である自分を、隠せば隠すほど、羞恥心は強化されていくものです。なぜなら、完璧ではない自分を必死に隠そうとすればするほど、常に「見破られるかもしれない」という怖れが伴い、その緊張感が羞恥心を増幅させるからです。
そして、考えてみれば、「恥ずかしい」という感覚は、一体、誰から受け継いでいるのでしょう?遠い昔には、恥のために「はらきり(切腹)」をする文化さえあったのですから、先祖代々、この感覚は文化や慣習として受け継がれているのかもしれませんね。
しかし、その「恥ずかしい」は、本当に、今を生きるあなたのものなのでしょうか?そして、たとえその「恥ずかしい」という感情を受け容れたところで、僕たちにどんな影響があるでしょうか?せいぜい数十秒の心拍数の増加くらいではないでしょうか。
僕自身、学生の頃、この羞恥心粉砕法を嫌というほど試しました。週末の夜の街に友人と出かけ、街行く女の子に声をかける実習に勤しんでいました。夏祭りがある時などは、わざわざ県外にまで足を伸ばし、「羞恥心」の限界を試したものです。
もちろん、僕たちのことをまるでゴミのように見る女子もいましたし、「あれ?石ころぼうしを被ってたっけ?」と僕に思わせるほど、僕の存在が無であるような錯覚に陥らせる女子もいました。
※【石ころぼうし】:石を模した表面を持つ半球型の帽子。これを被ると、まるで道端の石のように周りから一切認識されなくなり、自身の存在を完全に消すことができる。ドラえもんの道具のひとつである。(Wikipedia より)
この実習をし続けた結果、「恥ずかしい」という感覚は、自分が勝手に創り出している幻なのだと、心の底から理解できるようになりました。数年にわたるこの「切磋琢磨」は、今なお、僕にとって身を持って得たかけがえのない財産であり、感謝する日々です(苦笑)。
僕たちの「恥ずかしい」は、本当に誰のものなのでしょう?
そして、誰かから受け継いでいるのでしょうか?
その問いに、真剣に向き合った時、僕たちは、この幻から自由になる、本当の自分を見つけることができるのかもしれません。